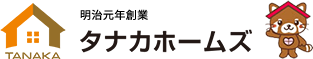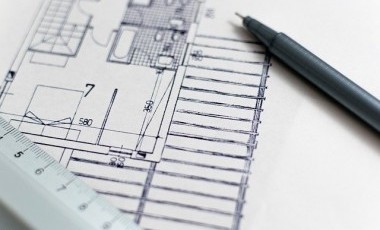Blog
スタッフブログ
-

2022年1月28日 / 家づくり
注文住宅の流れとは?プラン設計から竣工・引き渡しまでをわかりやすく解説
「家族構成が変わった」「会社が在宅ワークを導入した」など、ライフスタイルの変化に伴い住み替えを考える中で、戸建て住宅の購入を検討している人もいることでしょう。 この記事では、注文住宅の購入を検討している人向けに、注文住宅を建てる流れを解説します。 注文住宅の購入を検討する際の参考にしてください。 目次 1.注文住宅とは? 2.建売住宅との違い 3.中古リノベーションとの違い 4.注文住宅のプラン作成から竣工・引き渡しまでの流れ 5.注文住宅の購入から完成までの期間 6.注文住宅の支払いとローンの流れ 7.注文住宅の購入にかかる費用 8.まとめ 1.注文住宅とは? 注文住宅は、家を建てる人(施主)と施工会社が「建築工事請負契約」を結んで建築する新築の戸建て住宅です。 施主の要望にあわせてプランを作成するため、間取りや設備・デザインを自由に決められ、予算や生活スタイルに合わせやすいのが特徴です。 契約前に完成品を見られませんが、着工前に地盤調査をしたり、施工過程の確認はできます。 自分の目で確認しながら理想の住宅が建てられるでしょう。 2.建売住宅との違い 建売住宅は不動産会社などが土地を仕入れ、完成した住宅を土地とともに販売するものです。若干のプラン変更に応じてくれる場合もありますが、基本的に間取りや設備などは販売元の不動産会社が決めるため、注文住宅のような自由度はありません。 ただし、注文住宅に比べて安価な傾向があります。 3.中古リノベーションとの違い 中古リノベーションは、既存の建物に大掛かりなリフォームを行うものです。 耐力壁が抜けない、配管の関係で水回りの場所が限られるなどの制限もありますが、プランの自由度は高く、好みの間取りや内装が作れます。 注文住宅より安く、新築のような家が手に入ると注目されていますが、配管や躯体などは築年数に応じて劣化している可能性もあるため注意が必要です。 4.注文住宅のプラン作成から竣工・引き渡しまでの流れ 注文住宅を建てる際の流れについて解説します。 STEP1:不動産会社や施工会社に相談 工務店やハウスメーカーなど、注文住宅を取り扱っている会社に相談します。 気になる会社の店舗やオープンハウスへ足を運んだり、資料を請求したりしながら理想に近い住宅を建てている会社を選びましょう。 土地も一緒に探している場合は、不動産会社に声をかけ、土地を探しながら工務店などを紹介してもらう方法もあります。 STEP2:希望プランの選定 希望を伝え、プラン案の作成を依頼します。希望の間取り、予算、立地といった住宅に関する情報から、家族構成や趣味・趣向といったものまで、さまざまな情報を伝えることで、ライフスタイルにあったプランを提案してもらえるでしょう。 複数の会社に声をかけ、プランを見比べたり、親身に対応してくれるかを見極めることもおすすめです。 STEP3:見積もりやローン試算 希望のプランができたら、費用の見積もりを取ります。 プランの内容によって費用が変わるため、複数のプランに対して見積もりの作成を依頼するとよいでしょう。 おおよその金額がわかったら、自己資金がどれくらいあるのか、どれくらいの借り入れが必要かなどを検討します。 ローンを利用する際は、月々の返済額も試算してもらいましょう。 STEP4:敷地調査 購入を検討している建築予定の土地や、所有している土地の調査を行います。 建築条件にあわずプランが見直しになったり、地盤が弱く追加工事が発生したりする可能性もあります。 条件を満たすプランや見積もりを、改めて作成してもらいましょう。 土地を探している人は、先に希望プランを作り、プランにあわせて土地を探すことも可能です。 STEP5:申し込み 建築予定地を確認し、希望のプランが建築条件を満たすことを確認できたら、申し込みをします。 複数の会社を比較、検討していた人も、このタイミングまでに1社に絞りましょう。 申し込みには「申込金(手付金)」が発生する場合もあるため、事前に確認しましょう。 STEP6:ローン審査 申し込みをした会社に紹介されたりすでに取り引きがあったりする金融機関を選んで、正式にローン審査を行います。 自分で金融機関を探す場合は、金利や抵当権の設定費用、万が一の際の保険などを考慮しましょう。 希望どおりにローン審査が通らなかった場合は、金融機関や条件を変えて借入先を探すことになるため、時間がかかることもあります。 STEP7:プラン確定・最終見積もり 自己資金や借入金などの資金計画が立ったら、予算にあわせてプランを見直します。 最終的なプランをもとに見積もりを出し、プラン確定となります。着工後の変更に対応してくれる会社もありますが、プランが変更になると工期が延びる可能性が高いです。 細部までしっかり検討して、プランを確定させましょう。 STEP8:契約 プランや金額が確定したら、「建築工事請負契約」を締結します。 契約後に変更が生じた場合は、変更契約が必要になるため注意しましょう。 会社によっては、契約時にまとまった金額を支払う必要があったり、「仲介手数料」や「契約印紙代」などが発生したりする可能性もあります。 契約前に確認し、準備しておくと安心です。 STEP9:地鎮祭・着工・施工 地鎮祭を行い、近隣に挨拶をしたうえで着工します。 工事の進捗を確認しつつ、状況に応じて現地で打ち合わせをすることもあります。 現地へ足を運ぶ際は、近隣の方への気配りを忘れないようにしましょう。 近隣挨拶や工事中のフォローは施工会社が行います。施工中に気になる点や変更したい点が発生した場合は、担当者に相談してみましょう。 STEP10:竣工検査 建物の完成が近づいたら、竣工検査を行い施工に不備がないかを確認します。 竣工検査を通過すれば建物が完成となり、施主の立ち会いのもとで施主検査を行います。 不具合のない状態で引き渡しを受けるために、外構も含め細部までしっかり確認し、必要に応じて手直しを依頼しましょう。 また、建築基準法に基づいた完了検査も行います。 STEP11:引き渡し 施主検査を通過したら竣工・引き渡しとなります。 家の鍵や権利書といった重要書類、保証書や取扱説明書などを受け取りましょう。 引き渡し時に金融機関で決済を行い、施工会社へ注文住宅費用の残金を支払います。 引き渡しの手続きに必要なものは、事前に確認しておきましょう。 ローンの初回返済がいつかも確認しておくと安心です。 STEP12:引っ越し・入居 家には、引き渡し以降自由に出入りできます。 引き渡し当日に入居することも可能ですが、バタバタすることが予測できるため、数日〜1週間ほどの余裕をもって引っ越すとよいでしょう。 入居後の不具合は、契約内容や保障内容に基づいて対応してもらえます。 引き渡し時にアフターメンテナンスについても確認しておきましょう。 5.注文住宅の購入から完成までの期間 注文住宅の購入から完成までの期間は、1年が目安です。 しかし、「なかなかプランが決まらない」「ローン審査が通らない」といった理由で着工が遅れたり、仕様変更で工期が延びたりすれば1年以上かかることも少なくありません。 木造よりも鉄筋コンクリートのほうが施工期間は長めです。 入居したい時期が決まっている場合は、早めに準備を進めましょう。 スムーズに進められれば、購入から数ヵ月で完成し、入居できることもあります。 6.注文住宅の支払いとローンの流れ 注文住宅の費用の支払いや、ローンについて解説します。 h3:注文住宅を購入する際の支払い方法 注文住宅の購入費用の支払い方法は、主に現金とローンの2とおりがあります。 注文住宅は数千万円と高額な買い物になるため、一般的にはローンを組みます。 「建築工事請負契約」を締結する会社や契約内容にもよりますが、支払いは申込時・契約時・着工時・着工途中・竣工時などと段階を分けて行うことが多いです。 ローンを組む流れ 「購入したものの支払えない」ということがないよう、「建築工事請負契約」を結ぶ前にローン審査を行い、通過した場合に契約を結ぶのが一般的です。 しかし、実際にローンを受けられるのは竣工後となるため、竣工までの期間に支払いが発生した場合は、自己資金で支払うか、つなぎ融資を利用することになります。 つなぎ融資とは つなぎ融資とは、注文住宅の契約からローン開始までの間に受けられる一時的な融資のことです。 ローン開始前にまとまったお金が必要になる場合に利用し、ローン開始後に、借入金で返済するのが一般的です。 つなぎ融資を受ける会社とローンを組む会社が同じであれば、スムーズに返済ができるでしょう。 7.注文住宅の購入にかかる費用 注文住宅を購入する際にかかる費用の種類について解説します。 本体工事費 見積もりの大部分を占めるのが本体工事費です。 建物自体の費用で、仮設工事や基礎工事、構造体や屋根、内装、仕上げ、設備工事、水道管や電線の配管・配線工事などが含まれます。 本体工事費は1,500〜3,800万円ほどが一般的ですが、注文住宅の大きさや仕様などで変わります。 総工事費の75〜80%を目安に考えるとよいでしょう。 また、ハウスメーカーの坪単価や住宅価格は、本体工事費のみをもとに計算されていることが多いです。 付帯工事費 付帯工事費は、建物以外の工事にかかる費用のことです。 外構工事、水道管やガス管の引き込み工事、照明やエアコンといった設備の購入や取り付け工事などがあります。 そのほかにも、土地の状態によっては地盤改良工事が必要になったり、既存物件の建て替えでは解体工事が発生したりします。 状態によって異なるため具体的な金額を挙げるのは難しいですが、総工事費の15~20%ほどを目安に考えておくとよいでしょう。 諸経費 総工事費から本体工事費と付帯工事費を引いたものを諸経費といい、建物の登記や建築確認申請にかかる費用、印紙税、税金などを指します。 新居で使う家具の購入費や引っ越し費用なども諸経費に含まれます。 基本的に現金で支払わなければならないものが多いため、見積もり段階で予算をしっかり確保しておきましょう。 金額の目安は全体の5〜7%と言われていますが、余裕をもって10%ほど見積もることをおすすめします。 8.まとめ 注文住宅は、家を建てる人の希望にあわせて自由にプランを立てて建築する家です。 家族構成やライフスタイルに合わせて、長く住み続けられる家を探しているなら、注文住宅を検討してみることをおすすめします。 よい家を手ごろな価格で探している人は、創業150年の歴史をもつ、タナカホームズに相談してみてください。 高品質で高性能な住宅をローコストで提供しているタナカホームズなら、手ごろな規格住宅から完全自由設計の家まで、希望に沿った提案が可能です。 <<ここでしか見られない限定情報公開中 無料会員登録はコチラ>> 会社名:田中建設株式会社 部署名:編集部 執筆者名:大勢待 昌也 執筆者の略歴 保有資格 住宅ローンアドバイザー 執筆者のSNSのリンク:https://www.facebook.com/oosemachi
-

2022年1月28日 / 家づくり
失敗しない注文住宅のポイント
注文住宅の検討を始める際には、多くの夢や希望が膨らむ一方で、注意しなければならないポイントも多数存在します。この記事では、注文住宅の計画と建築でよくある失敗を避け、成功へと導く重要なポイントに焦点を当てて解説します。 1.失敗注文住宅の注意事項 2. 計画段階での失敗例 3. 施工時の注意点 4. 引渡し後のトラブル対策 1.失敗注文住宅の注意事項 予算管理の重要性 注文住宅の計画では、予算設定が最も重要です。現実的な予算を設定し、隠れたコストや予期せぬ支出に備えるために余裕を持たせることが重要です。 信頼できる工務店の選び方 工務店選びは、その後の建築過程全体の質を決めるため、信頼性や実績、対応の良さを評価することが大切です。 間取りの検討ポイント ライフスタイルに合った間取りを考慮することが重要です。将来の家族構成の変化も見据え、柔軟性のある設計を心掛けましょう。 地域の法規制に対する調査 建築予定地の法規制を理解し、計画が地域の規定に適合しているか確認が必要です。 2.計画段階での失敗例 プランの見直しの必要性 一度決定したプランでも、進行中に再評価することが必要な場合があります。柔軟に対応する心構えが重要です。 設備機器の選び方 長期的に使用する設備の選定には、耐久性やメンテナンスの容易さを考慮することが必要です。 耐震性についての考慮事項 地震国日本において、耐震性は無視できない要素です。最新の技術を取り入れ、安全性を高めましょう。 工期管理と工事監理の重要性 工期の遅延はコスト増加に直結します。しっかりとした工事監理を行い、計画通りに進行させることが重要です。 3.施工時の注意点 定期的な現場確認の必要性 自ら現場を訪れ、進行状況を確認することで、問題を早期に発見し対応が可能です。 材料や工法の品質確認方法 使用される材料や工法の品質を確認し、納得のいくものであることを保証しましょう。 変更時の契約内容の再確認 工事中に変更が必要になった場合は、その都度契約内容を確認し、追加費用の発生を避けましょう。 施工進捗の監理と報告 定期的な報告を受け、プロジェクトの進捗を把握しましょう。 4.引渡し後のトラブル対策 メンテナンス契約の重要性 定期的なメンテナンスは、長期的な住宅の品質を保つために不可欠です。信頼できる業者と契約しましょう。 建物保険の加入方法 建物保険に加入しておくことで、万が一の時の経済的負担を軽減します。 履行保証書の確認要点 工事完成後の履行保証書は、施工業者が提供する品質を保証する重要な文書です。その内容をしっかり確認しましょう。 住宅の定期的な点検と保全 定期的な点検を行うことで、問題を早期に発見し、修理が必要な状態になる前に対応します。 <<無料会員登録ですぐに見れるWebカタログはコチラ>> 会社名:田中建設株式会社 部署名:編集部 執筆者名:大勢待 昌也 執筆者のSNSのリンク:https://www.facebook.com/oosemachi
-

2022年1月28日 / 家づくり
【おしゃれな注文住宅を建てるなら】外観・内装で気をつけるべき点、設計のコツを解説
おしゃれな注文住宅を建てたいけれど、何に注意すべきなのかがわからないとお悩みの方は少なくないはず。 おしゃれだと感じる注文住宅は、どのようなことに気をつけているのでしょうか。 ここでは、注文住宅を建てる際に外観と内装で押さえたい点を紹介しています。 また、実際の住宅建設に向けて動くときのコツなども解説していますので、ぜひ参考にしてください。 目次 1.おしゃれな注文住宅を建てるために大切なこと 2.おしゃれな注文住宅を建てるためにぜひ知っておきたいこと 3.まとめ 1.おしゃれな注文住宅を建てるために大切なこと せっかく注文住宅を建てるなら、完成したときに親族や友人に自慢できるおしゃれな家にしたいものです。 ところが、おしゃれな家に憧れはあっても、具体的にどのような点に気をつければよいのかわからないという方が少なくありません。 ここでは、家の外観と内装それぞれで、おしゃれに見えるコツを解説します。 住宅の第一印象を決める外観 家の第一印象は外観で決まります。 家の形をはじめ、外観には屋根や壁の材質、色、外構、門扉の有無など、人目を引く要素が多く存在します。 来客や隣人に、こだわりの要素をアピールするために気をつけたい点を細かく解説します。 家のシルエットは長く愛着を持てるように 家の外観やシルエットはマイホームの印象を決定づける重要な視点です。 一方、リフォームやリノベーションで変更できる家の内部と異なり、外観やシルエットは簡単には変更できません。 そのため、あまり変わったデザインにせず、長く愛着が持てるようなデザインを意識しましょう。 デザインの組み合わせは無限とあるため、さまざまなパターンを検討しながら家族が長く愛せる家を作り上げてください。 外壁や屋根は周囲にうまくなじむように 外壁や屋根を考えるとき、素材はもちろん、色のイメージも大切な要素です。 家のシルエットと同様に、景観にうまくなじむように工夫してみてください。 素材と色味を工夫すれば、家のイメージを印象づけやすくなります。 外観でアピールしたいのは落ち着きなのか、スタイリッシュさなのかなど、与えたい印象をじっくり検討してみましょう。 窓はデザインと利便性にこだわって 窓について考えるときは、デザインとともに利便性にも注目することが重要です。 大きな窓は、自然光をうまく取り込めるうえ、開かれた印象を与えます。 しかし、ただ大きいことだけにこだわるとメンテナンスが難しくなるかもしれません。 いくら窓が大きく採光に優れていても、外から丸見えの室内では生活しにくいため注意しましょう。 また、思っていたように光を取り込めないというケースもあります。 窓のデザインを考える際は、土地の向きや太陽光の入り具合まで考慮しましょう。 外構は外部からの視線を上手に避けられるように カーポートやエクステリアといった外構は、その注目住宅ならではのこだわりをアピールできる要素です。 門やフェイス、庭、ガレージといった建物以外の要素にも力を入れることで、外観のおしゃれさが際立ちます。 隣家からどのように見えるか、使い勝手のよさはどうかなどをじっくり考えたうえでデザインしましょう。 内装はセンスのよさと使いやすさを両立させて 内装を整えるうえでは、センスのよさと使いやすさの両立を目指すようにしましょう。 内装次第で、圧迫感がなくなり広がりのある空間を作り上げることができます。 すっきりとした印象を与えるためには、リビングや階段、フローリング、壁といった要素に統一感を持たせ、バランスを取ることが大切です。 間取りは圧迫感のなさと通気性のよさを大切に 間取りを考える際は、圧迫感がないように気をつけながら、通気性を高める工夫を凝らしましょう。 間取り次第で家に入ったときの来客の印象が大きく変化します。 吹き抜けを取り入れたり、視線をうまく誘導することで家の内部を大きく見せられます。 また、中庭やバルコニーなどを利用して家の内部と外部とがつながるように設計すれば、日当たりや通気性を確保できます。 内装は配色やインテリアの統一感が重要 内装を考えるうえで重要なのは、配色やインテリアの統一感です。 ひとつひとつのインテリアが綺麗で整っていても、配色がバラバラではアンバランスな印象を与えてしまいます。 インテリアを使って家全体のテイストをまとめるように意識しておけば、比較的簡単に統一感を出せます。 照明を使ってメリハリのきいた空間に 一般的な日本の住宅では、家全体や部屋全体を明るく照らす照明が大半を占めています。 しかし、スタンドやダウンライトといった間接照明を取り入れることで、メリハリのきいた空間が作れます。 埋め込み式のダウンライトや透明なガラスを用いた照明なら、日中でも視線を邪魔することがありません。 いざ配線などが終わった段階で照明を変更したいと思っても、なかなか難しいケースがあります。 最初から綿密な計画を立てて、部屋の使い方や目的に合わせた照明を配置できるようにしましょう。 階段は調和性と安全性、部屋全体の開放感に注目 階段は、そのデザイン性もさることながら、部屋との調和性と安全性にぜひ気をつけたい要素です。 階段の色を部屋内部の色を統一することで、部屋全体の広がりを感じられるなど、階段のデザイン次第で室内の印象が一変します。 また、小さな子どもやご年配者への配慮も大切です。 毎日安心して上り下りできるような工夫をしましょう。 水回りでは機能性と美しさを両立 お風呂やキッチン、洗面所、お手洗いといった水回りは、毎日頻繁に使う場所です。 それだけに、美しさと同時に使いやすさを実現できる場所であることが重要です。 十分な収納場所を設けたり、動線が重なったりしないように工夫をしてみましょう。 また、見た目をすっきりさせることで掃除が楽になり、清潔感を保ちやすくなります。 2.おしゃれな注文住宅を建てるためにぜひ知っておきたいこと デザインにこだわりたいけれど、あちらこちらでそのこだわりを形にしたことで、チグハグな印象になったという方が少なくありません。 決められた予算の中で、満足のいく家が建てられそうにないといった悩みもあるでしょう。 ここでは、満足のいくおしゃれな注文住宅を建てようというとき、ぜひ知っておきたいことを4つ挙げ、わかりやすく解説します。 自分の好みを知る 注文住宅を建てる最初の第一歩は、自分の好みを知ることです。 さまざまな情報があふれている中で、自分の好みのスタイルが何か、自分が落ち着いて過ごせる空間とはどのようなものかを確かめてみましょう。 そのためにも、自分が気に入ったインテリアの写真などを集め、どこが好きなのかを書き出していくと、好みがはっきりします。 好みをしっかり把握するためには、なるべく多くの事例を見ることがおすすめです。 住む人との相性を考える 小さな子どもやご年配者がいる場合は、デザイン性よりも安全面への配慮が重要です。 例えば見た目がすっきりとした階段ではあるものの、手すりがない・滑りやすい作りでは事故につながる原因になります。 その家に住む方との相性を考え、好みのデザインとどう折り合いをつけていくか考えましょう。 優先順位を決める 「家の細部にこだわり続けた結果、予算が足りなくなった」そのような事態に陥る方が少なくありません。 予算との兼ね合いを考えながら、どこまで何にこだわるかを家族で検討しておきましょう。 そのうえで、どうしても譲れないところにコストをかけられるよう、優先順位を決めコスト配分を考えておくことが重要です。 設計・施工するハウスメーカーを厳選する 施主の要望をかなえられるかどうかは、建設業者によっても左右されます。 思いどおりの注文住宅を建てるためには、施主の意見にしっかり耳を傾けてくれ、要望を実現するための柔軟さと実力を持った建築業者が不可欠です。 どのような家にしたいのかを思い描くと同時に、その青写真を実現できるハウスメーカーを厳選しましょう。 3.まとめ ここでは、おしゃれな注文住宅を建てたいとお考えの方に向けて、こだわるべき箇所と注意すべき点について解説しました。 おしゃれな注文住宅づくりをするうえで、信頼のおけるハウスメーカー選びは非常に重要です。 施主の要望と予算との兼ね合いを考え、提案してくれるハウスメーカーを選べるかどうかが、最終的なカギといってもいいでしょう。 タナカホームズでは、ローコストでありながらも高品質・高性能な注文住宅を実現できます。 おしゃれな注文住宅づくりを希望している方は、ぜひご検討ください。 <<来場予約はコチラ>> <<ここでしか見られない限定情報公開中 無料会員登録はコチラ>> 会社名:田中建設株式会社 部署名:編集部 執筆者名:大勢待 昌也 執筆者の略歴 保有資格 住宅ローンアドバイザー 執筆者のSNSのリンク:https://www.facebook.com/oosemachi
-

2022年1月28日 / 家づくり
2,000万円の注文住宅の間取りや予算内で建てるための6つのコツを解説!
注文住宅の建築の予算を2,000万円程度で検討している人もいるでしょう。 2,000万円の注文住宅は間取りがどの程度なのか、十分な空間が取れるかなど気になるものです。 この記事では、2,000万円の注文住宅の建築を検討している人に向けて、必要な費用の内訳や間取りの具体例などを紹介します。 また、予算内で建築するコツなども解説しています。 ぜひ参考にしてください。 目次 1.注文住宅の建築にかかる費用の内訳 2.2,000万円の注文住宅はどれくらいの間取りになる? 3.注文住宅を2,000万円以内で建てるときの6つのコツ 4.2,000万円以内で注文住宅を建てるときの注意点 5.まとめ 1.注文住宅の建築にかかる費用の内訳 注文住宅は建築を検討する人の予算に応じて建築費用を調整できることが特徴です。 注文住宅の建築費用は、1,000万円前後から上限なしまで予算の幅が広いです。 なかでも、土地代を除いて2,000〜3,000万円台の注文住宅を検討する人が多くいます。 注文住宅の建築には、土地や建物(家)の購入費用などがかかります。 そのほかにも駐車場などを希望するときは、付帯工事の費用も発生します。 まずは注文住宅の建築にかかる費用を理解していきましょう。 土地の購入にかかる費用 住宅を建築するための土地を保有していない場合は土地の購入費用が発生します。 土地の購入には、手付金や購入に関する諸経費も必要です。 購入諸経費は、建物や建物周辺の工事にかかる費用以外の費用で、具体的には住宅ローン締結時の手数料や保証料、仲介手数料などが該当します。 なお、土地の購入にかかる費用は、国土交通省が発表している地価調査の最新版や土地総合情報システムを活用すると目安がわかります。 ※参考:「令和2年都道府県地価調査」21住宅地の圏域別・地方別平均価格 表8|国土交通省 ※参考:土地総合情報システム 家の建築にかかる費用 家の建築にかかる費用には、建築会社との工事契約金、建築確認申請費用、着工金、各儀式の際にかかる費用、登記費用などがあります。 また、住宅ローンを組む際は、借入時の費用も発生します。 ローンの借入費用は、事務手数料や保証料、火災保険料などが発生します。 注文住宅の新築では家の建築費用が最も高い割合となり、土地代を除く予算の7〜8割程度に及びます。 付帯工事にかかる費用 付帯工事には、庭や駐車場の造成費用、門や塀の工事費用、通信回線や水道管などの引き込み費用などが含まれます。 建替えの場合はもとの家の解体費用も必要など、付帯工事には何かと費用がかかるものです。 そのため、建物本体以外にかかる費用を事前に検討する必要があります。 付帯工事の費用は、土地代を除く予算の2割程度が目安と考えておきましょう。 2.2,000万円の注文住宅はどれくらいの間取りになる? 土地の購入費用や付帯工事により異なりますが、2,000万円の予算の注文住宅では3LDKや4LDKの間取りにすることが可能です。 場合によっては部屋数を増やして6LDKの間取りにできる場合もあります。 しかし、2,000万円の注文住宅は、理想をすべて叶えようとすると予算を超えてしまう価格帯です。 「内装を妥協して、バスルームを理想のものにする」など、バランスを考えたいところです。 ここからは坪数ごとに予算内に収まる具体的な間取りを紹介します。 30坪以下の間取り 30坪以下の場合は、坪単価60万円以下の業者を検討してください。 また、30坪以下であれば、2LDKの間取りに適しています。 30坪以下というと手狭に感じますが、3人家族で収納スペースを2〜4畳ほど確保してもリビングを16〜18畳ほどにできます。 洗濯物を外に干したい場合は、バルコニーの採用も検討しましょう。 30~35坪の間取り 30〜35坪の場合は、坪単価50万円前後の業者を検討してください。 この坪数は家族3〜4人で暮らす広さである3LDKの間取りに適します。 広めのリビングにした場合でも、各部屋6〜10畳ほどの広さが確保できます。 また、35坪前後の建物では、3部屋のほかに収納など希望にあった空間を設けることが可能です。 各空間の使い方を検討してみてください。 35~40坪の間取り 35〜40坪の場合は、坪単価45万円前後の業者を検討してください。 坪数も多いため5人家族でも十分に暮らせる4LDKくらいの広さになります。 リビングを20畳ほどにしても、各部屋を10畳まで広げることが可能です。 8畳や10畳の部屋であれば、室内の収納にも余裕が生まれます。 広い空間をどのように活用するか考えてみましょう。 40坪以上の間取り 40坪以上の場合は、坪単価40万円前後の業者を検討したいところですが、対応できるハウスメーカーが限られてくるでしょう。 特に50坪以上では2,000万円で注文住宅を建てることが難しくなります。 最大でも45坪までにするといいでしょう。 しかし、40坪以上ならば2世帯住宅にすることが可能です。 15畳前後のリビングが2つと、6畳前後の部屋を4つ程度の広さを確保できます。 3.注文住宅を2,000万円以内で建てるときの6つのコツ 2,000万円という限られた予算で注文住宅を建てるときは、これから紹介する6つのコツを覚えておきましょう。 以下でそれぞれの内容を解説します。 予算配分を考える 注文住宅の建築にはさまざまな費用がかかります。 予算配分の目安は住居本体の工事費用が7割、付帯工事が2割、諸経費が1割となります。 たとえば、住居本体が1,000万円ならば、10%分である100万円を諸経費として残りの900万円で付帯工事と土地代をまかなう計算です。 ただし、この予算配分には家具や家電の購入費用が含まれていません。 新築に伴い家具や家電を新調する際は、予算配分に入れ込むか、建築費とは別に予算を確保する必要があります。 間取りや建物で妥協点をみつける 2,000万円の予算で間取りなどの希望を列挙しすぎると、簡単に予算をオーバーします。 そのため、建材や設備のグレード、間取りなどで妥協する必要があります。 妥協点をみつける際は、理想として譲れない部分を決めるといいでしょう。 その後、間取りの広さや妥協できる箇所のグレードを落としてみてください。 また、新築時にコストをおさえて金銭的に余裕がでてきたときにリフォームすることも可能です。 できるだけシンプルな家にする 建物の形状や間取りをシンプルにすることで、費用をおさえることも可能です。 たとえば、1階と2階の大きさや形が同じ建物は屋根材や外壁材を使う量が少なくなり、費用も少なくなります。 内装では、段差を少なくしたり仕切りを減らしたりすると、建築費用をおさえられるでしょう。 できるだけシンプルなつくりを検討してみてください。 平屋構造も検討する 住宅を平屋にする際は広い土地が必要となりますが、土地の形状や地域などにより土地代をおさえることが可能です。 平屋は2階が不要なため、建築時の足場費用がかからないケースがあります。 ただし、延べ床面積によっては2階建てよりも多くの費用がかかることが考えられます。 業者からの見積もりなどで判断してみてください。 付帯工事費用を見直す 付帯工事の費用は建築時の予算の2割ほどが目安になりますが、予算配分を見直すことで費用をおさえることができます。 たとえば、駐車場の舗装の種類やルーフの有無などを見直してみてください。 門や外壁では素材のグレードを下げるなど、付帯工事においても妥協点を検討しましょう。 複数の業者に見積もりを依頼する 理想や条件が同じでも、業者により見積もり金額が異なる場合があります。 そのため、同じ条件で複数の業者から相見積もりをとることをおすすめします。 複数の見積もりをとると、安くて理想を実現できる業者をみつけやすいです。 業者に見積もりを依頼するときは、家づくりの希望条件をリストアップしておき、間取りや設備などを反映してもらいましょう。 業者に詳細な理想を伝えることで、正確な見積もりにつながります。 4.2,000万円以内で注文住宅を建てるときの注意点 注文住宅を建てた後に後悔しないために、可変性のある間取りにしたり家事動線と生活動線に配慮したりすることが大切です。 たとえば、建築時は「造り付け家具が便利」と感じても住みはじめてから「模様替えができない」など不便さを感じることもあるでしょう。 そのときどきの流行などに惑わされず、自分や家族のライフスタイルに合わせた間取りにしてください。 収納を検討する際は玄関ならば靴やコート掛け、リビングは新聞や雑誌、子ども部屋は学用品など収納するモノとスペースの確保を考えましょう。 5.まとめ 注文住宅を建築する際は、土地や建物の費用、付帯工事費用がかかります。 2,000万円の予算におさめるには、予算配分を決めることが大事です。 また、坪数に応じて確保できる間取りが異なるため、理想をリストアップしてみましょう。 その後、複数の業者に見積もりを依頼して、納得のいく業者を選んでください。 タナカホームズでは、ローコストで高品質、高性能な住宅を建築します。 2,000万円の注文住宅のご依頼も可能です。この機会にぜひご相談ください。 会社名:田中建設株式会社 部署名:編集部 執筆者名:大勢待 昌也 執筆者の略歴 保有資格 住宅ローンアドバイザー 執筆者のSNSのリンク:https://www.facebook.com/oosemachi
最近の投稿