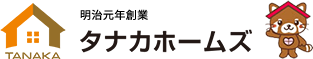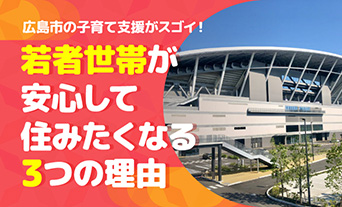Blog
スタッフブログ
-

2025年6月27日 / 土地
広島市の「もしも」に備える!ハザードマップで家族を守る安心の家づくり(津波リスク編)
2025年3月に政府が南海トラフ地震の新たな被害想定を公表し、広島県の津波被害が大きくなりました。 そのため、これから広島県で注文住宅を建てる予定の方は、ハザードマップで津波による浸水区域を調べた上で安全な土地を選ぶようにしましょう。 今回はハザードマップで広島市の津波リスクを確認する方法をご紹介します。 ぜひ家族を守る安心の家づくりにお役立てください。 目次 1.広島市の津波リスクを正しく知ろう 2.津波ハザードマップの使い方【初心者向け】 3.津波に備えてできること 4.まとめ 1.広島市の津波リスクを正しく知ろう まずは、大地震が発生した際に広島市にどれぐらいの被害が及ぶのかを知りましょう。 ここでは、過去の地震や南海トラフ地震などの観点から広島市の津波リスクを解説します。 広島市で津波は起きうる?地形と過去の記録から考える 広島県に被害をもたらした主な地震は以下の通りで、津波による被害の記録は極めて少ないと言われています。 ■広島県に被害を及ぼした地震 しかし、30年以内に80%程度の確率で訪れると予想されている南海トラフ巨大地震はマグニチュード9クラスと言われています。*1 これまでの地震よりもエネルギーが大きく、津波による被害が発生すると推計されているため注意しておくことをおすすめします。 南海トラフ巨大地震が起きた場合の被害予想*2 近い将来、発生が懸念されている南海トラフ巨大地震(マグニチュード9クラス)が発生した場合、広島県の死者は最悪の場合、およそ2,200人にのぼると国が試算されています。 広島県は津波で30センチ以上浸水する範囲は2,910ヘクタール、約7割にあたる約1,500人が津波による犠牲者と想定されています。 一方で、対策で被害を減らせる推計も行っており、多くの人が地震直後に避難できた場合は津波による死者数は60人までに減らせると発表しました。 国の想定に対して、広島県はさらに大きな被害が想定しており、犠牲者は最大1万4,000人を超えると発表しています。 甚大な被害をもたらすため、これから注文住宅を建てる方は津波リスクが低い土地に家を建てることをおすすめします。 2.津波ハザードマップの使い方【初心者向け】 これから注文住宅を建てる方は、ハザードマップを使用して津波リスクの低い土地を選ぶようにしましょう。 ここでは、気になる場所の津波リスクを確認できるハザードマップの入手方法や見方についてわかりやすく解説します。 どこで見られる?津波ハザードマップの入手方法 津波のハザードマップは、国土交通省が一般公開している『ハザードマップポータルサイト』で入手できます。 ポータルサイト上で災害リスクを調べたい地点の住所を入力すれば、危険区域かどうかを誰でも簡単に調べられます。 ぜひ、ハザードマップポータルサイトを閲覧してみてください。 また、広島県が津波災害警戒区域に指定した市役所では津波ハザードマップを作成し,配布しています。 津波発生時の避難のアドバイスなども受けられるため、詳しく聞きたい方は市役所の危険管理課を訪問してみることをおすすめします。 ハザードマップの色分けと見方 出典:国土交通省『ハザードマップポータルサイト』 ハザードマップを使用すれば、津波浸水想定エリアと深さが一目でわかります。 広島港の周囲はオレンジ色になっており、津波により1階天井もしくは2階の軒下まで浸水すると予想されています。 浸水想定区域で土地を購入する場合、購入するべきか判断する一つの目安が浸水深が3.0mを超えるかどうかです。 浸水深さが3.0mを超えると、2階まで浸水して生活できなくなるため、このような場所に注文住宅を建てるのは避けた方が無難です。 避難経路や避難場所をあわせてチェック 出典元:広島市役所『わがまち防災マップ』 ハザードマップと併せて確認しておきたいなのが、各自治体が公開しているわがまち防災マップです。 自然災害時に住民の命が助かるように、危険区域や避難場所、避難経路などを公表しています。 津波が発生した際にどこに避難すればよいかのか書いているため、あわせてチェックするようにしましょう。 3.津波に備えてできること 津波に備えて対策をすれば、家族を守る安心の家づくりができます。 ここでは、津波に備えてできることをご紹介します。 土地選びでできる津波リスクの回避法 津波被害が心配な方は、ハザードマップで浸水想定区域や過去の災害情報を調べた上で安全な土地を選ぶようにしましょう。 沿岸から離れていて、標高の高い土地を選ぶと津波による被害の心配をせずに済みます。 また、避難路の整備が進んでいる地域を選ぶと、より安心して暮せることでしょう。 大地震による津波など自然災害が不安な方は、自治体の防災担当者に相談して、どのエリアが安全なのかアドバイスをもらうのもおすすめです。 災害時に命を守るための行動と準備 家族の命を守るために、津波警報時にどのような行動を取るべきかを学び、準備しておきましょう。 大切なことは、地震の揺れを感じたときは、直ちに海浜から離れて高台など安全な場所へ避難することです。 各自治体が公開しているわがまち防災マップには、津波発生時の避難場所が記載されているため必ずチェックしておきましょう。 また、非常時の持ち出し品を準備しておき、指定場所に保管しておきます。 【非常時持ち出し品リストの例】 □ 現金・預金通帳 □ ラジオ・電池 □ 懐中電灯 □ 水・非常食 □ 救急箱 □ 防寒着・替えの下着 4.まとめ 近い将来、発生が懸念されている南海トラフ巨大地震(マグニチュード9クラス)が発生した場合、津波で30センチ以上浸水する範囲は2,910ヘクタール、約7割にあたる約1,500人が津波による犠牲者となると予想されています。 一方で、対策で被害を減らせる推計も行っており、多くの人が地震直後に避難できた場合は津波による死者数は60人までに減らせると発表しました。 つまり、家族の命を工夫次第で守ることができます。 そのため、これから家を建てる予定の方はハザートマップを活用して、安心して住める土地かどうかを確認してみてください。 タナカホームズは震災に強い家づくりを得意としています。 そのため、ご興味がある方はぜひお気軽にご相談ください。 <<ここでしか見られない限定情報公開中 無料会員登録はコチラ>> 会社名:田中建設株式会社 部署名:経営企画部 執筆者名:大勢待 昌也 執筆者の略歴 保有資格 住宅ローンアドバイザー 執筆者のSNSのリンク:https://www.facebook.com/oosemachi 引用 *1南海トラフ巨大地震 今後30年以内の発生確率「80%程度」に引き上げ 日向灘で13日に起きた地震は影響せず | NHK | 南海トラフ地震臨時情報 *2南海トラフ地震 国が新被害想定 広島県の死者約2200人|NHK 広島のニュース
-

2025年6月25日 / 土地
広島市の「もしも」に備える!ハザードマップで家族を守る安心の家づくり(洪水リスク編)
大雨警報が発表されるほどの豪雨では、川の氾濫や土砂崩れなどの被害が及ぶ恐れがあります。 実際に東広島市平成30年7月豪雨災害では甚大な被害が発生しました。 そのため、土地を探す際にはハザードマップを活用し、自然災害のリスクが低いかを確認しましょう。 今回はハザードマップで洪水リスクを調べる方法を紹介します。 家づくりの際にできる洪水対策も併せて紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。 目次 1.そもそもハザードマップってなに?どう使うの? 2.広島市の洪水リスクは?安全なエリアはどこ? 3.洪水に備えてできること 4.まとめ 1.そもそもハザードマップってなに?どう使うの? まずは、ハザードマップとはなにか、どのように使うのか基本をわかりやすく解説します。 知っておきたいハザードマップの基本 ハザードマップとは、国や自治体など公共機関が提供している防災情報です。 日本は台風や地震など自然災害が発生しやすい国であるため、いつ災害が起こってもおかしくありません。 そこで、公共機関は自然災害による被害を最小限に抑え、人々を守るために危険区域や避難場所、避難経路情報を公開しています。 ハザードマップは2種類あるため、それぞれの特徴を理解しておきましょう。 (1) 重ねるハザードマップ 出典:「ハザードマップポータルサイト」 国土交通省が提供している防災情報です。 地図に「洪水」「土砂災害」「高潮」「津波」の危険区域を重ねて表示することができます。 災害が少ない場所を確認できるため、家族が安心して住める土地を探す際に役立ちます。 (2) わがまち防災マップ 出典:「わがまち防災マップ(東荒神町町内会)」 各自治体が提供している防災情報です。 各自治体で情報が異なりますが、危険区域、避難場所、避難経路、避難情報の入手方法などがわかりやすくまとめられています。 災害時にどこに避難すべきなのか家族で確認しておくと、いざという時に安心です。 どこで入手できる?広島市のハザードマップ入手方法 広島市のハザードマップはWebサイトから入手できます。 ・重ねるハザードマップの入手方法 国土交通省が運営する『ハザードマップポータルサイト』 ・わがまち防災マップの入手方法 広島市役所が運営する『防災情報サイト』 また、広島市役所の地域起こし推進課の窓口でも、わがまち防災マップを配布しています。 ハザードマップの閲覧方法などアドバイスを受けられるため、防災対策をしたい方は事前予約して訪問してみると良いでしょう。 2.広島市の洪水リスクは?安全なエリアはどこ? 次に、広島市で洪水被害が及ぶ危険区域、安全なエリアをハザードマップで調べる方法をご紹介します。 ハザードマップを使った洪水リスクの調べ方 1.国土交通省が運営するハザードマップポータルサイトを立ち上げる 出典:「ハザードマップポータルサイト」 2.自然災害時の危険度を調べたい場所の住所を入力して検索する 出典:「ハザードマップポータルサイト」 3.左上にある災害マークから「洪水」を押す 出典:「ハザードマップポータルサイト」 4.特定の場所の自然災害リスクを把握する 出典:「ハザードマップポータルサイト」 ※広島市役所が運営する『防災情報サイト』から、わがまち防災マップを取得して危険区域や避難場所、避難経路を確認しておくとより安心できます。 比較的リスクが低いとされる地域の特徴 広島市内でも河川や海との距離、地形により洪水リスクに差が出ます。 広島市は水の都とも呼ばれており、多くの川が流れています。 特に太田川とその分流である6本の川が有名です。 河川の近くは洪水浸水想定区域(洪水によって想定される浸水深5.0~10.0m)となっています。 そのため、河川から離れていて緩やかな丘陵地を選ぶことをおすすめします。 注意すべき意外な盲点エリアとは 河川から離れており、緩やかな丘陵地だから安心とは言い切れず、次のような盲点となりやすいエリアにご注意ください。 内水氾濫し冠水する恐れがある都市部の低地 土砂崩れの被害に見舞われやすい山の麓や急傾斜地 液状化現象や地盤沈下により家が傾く恐れがある埋め立て地 集中豪雨で洪水の被害が及びやすい小規模河川の近くの地 地域の防災資料から地形情報、過去の災害履歴なども調べておくことをおすすめします。 3.洪水に備えてできること 注文住宅を検討している方の中には、既に土地をお持ちの方もいるでしょう。 所有している土地が洪水の影響を受けやすい場合でも、洪水に備えて対策しておけば安心して住むことができます。 ここでは、洪水に備えてできることをご紹介します。 家づくりの際にできる洪水対策 家づくりの際にできる洪水対策は5つあります。 (1) かさ上げ(盛り土)して敷地全体を高くする かさ上げして敷地全体を高くすれば浸水被害を防ぐことができます。 盛土工事を行う際は、不同沈下を引き起こさないように締め固めを行うことが大切です。 また、盛り土が崩れ落ちるのを防ぐために十分な強度を持つ擁壁を築く必要があります。 盛土工事は予想よりも高額になる場合が多いため、費用対効果も含めて総合的に判断することをおすすめします。 (2) 高床構造を採用する 基礎を高くしたり 、ピロティ構造 (1階部分は柱のみの構造で、2階以上を居住スペースにする建物構造)を採用したりして建物を高くすれば、浸水被害を防ぐことができます。 しかし、耐震性が低くなったり、バリアフリーの観点からみると不便に感じたりしやすいです。 (3) 防水性の高い外壁材を使用する 1階部分の外壁に防水性の高い外壁材を使用することで、住宅内へ雨水が浸入するのを防げます。 防水性の高い外壁材にはアクリル系、ウレタン系、シリコン系、フッ素系、遮熱系(サーモアイウォール)、ラジカル系、無機系などがありますが、コストや耐久性などが異なるため、専門家に相談するようにしましょう。 また、1階部分の腰壁をRC造にする方法もあります。 (4)2階だけで生活できるようにする 2階だけで生活できるようにしておけば、1階が浸水した場合でも日常生活を送ることができます。 しかし、電力を各部屋に供給する分電盤が床下浸水すると電気が使えなくなります。 そのため、1階と2階に分電盤を設置しておき、自然災害時でも電気を確保できる状態にしておきましょう。 (5)火災保険に水災補償をつける 住宅ローンを組む際に火災保険の加入が義務付けられていますが、水災補償はオプション となっています。 そのため、台風や豪雨による被害が不安な方は火災保険に水災補償を付帯しておくことをおすすめします。 大雨や台風で住宅に被害が及んだ際に修繕費用だけでなく、仮住まい費用も発生するため、きちんと備えておきましょう。 防災情報や備蓄の準備を忘れずに 災害に見舞われた場合でも、慌てずに行動することが大切です。 そのため、防災情報や備蓄の準備を忘れずにしておきましょう。 (1) 災害情報の取得 ハザードマップを確認して自宅が災害リスクにさらされているかを確認しておきましょう。 また、わがまち防災マップを見て避難場所や避難経路を確認しておくことで、いざというときに落ち着いて行動できるようになります。 正しい知識と備えがあれば、被害を最小限に抑えることはできます。 そのため、防災に関する知識を身につけておきましょう。 (2) 食料や生活用品などの備蓄 災害時は流通が止まるため、3~7日分の食料や生活用品を備えておきましょう。 防災グッズは、いざというときにすぐ使えるように置き場所も決めておくことをおすすめします。 <家庭内備蓄> □ カセットコンロ □ 簡易食器 □ 缶詰・レトルト食品など □ スープ・みそ汁など □ チョコレート・あめ・スナック菓子など □ 水(1人1日3リットル) □ トイレットペーパー □ ウエットティッシュ □ ビニール袋・ごみ袋 □ ランタン □ ラジオ □ 携帯電話充電器(電池式) □ 乾電池 □ 洗面用具 □ 簡易トイレ □ 救急セット・家庭用常備薬・マスク □ 工具類(ロープ、バール、スコップなど) □ ヘルメット・軍手・懐中電灯 □ 貴重品(通帳・印鑑など) □ 現金 □ 健康保険証・運転免許証などのコピー □ 上着・下着 □ 雨具 4.まとめ 家族が安心して暮らせる家をつくるために、災害が少ない区域の土地を探しましょう。 ハザードマップを活用すれば、検討している土地の災害リスクを確認できます。 また、家づくりの際にできる洪水対策、防災情報や備蓄の準備方法も併せてご紹介しました。 この記事が、万が一に備えて家族が安心して暮らせる住まいづくりにお役に立てれば幸いです。 また、洪水リスクに備えた家づくりにご興味がある方は、ぜひタナカホームズにご相談ください。 <<ここでしか見られない限定情報公開中 無料会員登録はコチラ>> 会社名:田中建設株式会社 部署名:経営企画部 執筆者名:大勢待 昌也 執筆者の略歴 保有資格 住宅ローンアドバイザー 執筆者のSNSのリンク:https://www.facebook.com/oosemachi
-

2025年6月18日 / 暮らし・育児
広島市の子育て支援がスゴイ!若者世帯が安心して住みたくなる3つの理由
広島市では若者世帯が安心して妊娠、出産、子育てができるようにさまざまな支援が提供されています。 子育てを意識して引っ越しを検討している方は、広島市を候補に入れてみてはいかがでしょうか? 今回は広島市の子育て支援制度について解説します。 子育てにおすすめのエリアも併せて紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。 目次 1.広島市の子育て支援制度 2.利用者に好評!紙おむつのサブスク 3.子育て応援アプリ『母子モ』 4.子育てにピッタリのエリアは?広島市内のおすすめ地域 5.まとめ 1.広島市の子育て支援制度 まず、広島市では「出産・子育て応援給付金」「こども医療費の補助」といった経済的支援が提供されています。 出産・子育て応援給付金 出産・子育て応援給付金とは、妊娠中や子育て中の方に対する経済的支援です。 所得制限はなく、誰でも経済的支援が受けられます。 ・子育て応援給付金 広島市役所に妊娠届を提出し、保健センターで面談を受ければ、妊婦1人につき5万円の現金が受け取れます。 ・出産応援給付金 2023年3月以降に出生した児童を養育 しており、新生児訪問やこんにちは赤ちゃん事業等で面談を受ければ、児童1人につき5万円の現金が受け取れます。 ※他の市町村で子育て応援給付金を受け取った方は対象外となります。 こども医療費の補助 こども医療費の補助とは、中学校3年生未満のこどもが医療機関を受診した際の自己負担額を軽減する補助制度です。 医療機関の窓口で、こども医療費受給者証とマイナ保険証を提示すれば、限度額までの負担のみで診療が受けられます。 「扶養親族等の数」「所得額」などにより、自己負担額が変わるため、下記の表でご確認ください。 2.利用者に好評!紙おむつのサブスク 2025年4月から広島市の保育園・認定こども園(全86園)では、0歳児・1歳児クラスの園児の保護者を対象に紙おむつやおしりふきが定額で使い放題となるサブスクリプションサービスが提供されています。 初月は無料で、翌月以降から月額2,180円(税込)を支払えば、紙おむつやおしりふきが使い放題です。 赤ちゃんのおむつ代は月5,000円~7,000円はかかるため、サブスクリプションサービスを利用すれば節約できます。 実際にサービスを利用している方からは「急にサイズアップしてもすぐ対応してもらえる」「外出の際のおむつストックが心配でなくなった」といった喜びの声も上がっています。 3.子育て応援アプリ『母子モ』 広島市では、ひろしま子育て応援アプリ『母子モ(ははこも)』を提供しています。 このアプリを利用すれば、スマートフォン上で妊婦健診の記録や予防接種のスケジュール管理やこどもの成長の記録ができます。 また、広島市からのお知らせも受け取ることも可能です。 初めての子育てはわからないことだらけで不安になりますが、アプリを利用すれば必要な情報が収集できて安心できます。 4.子育てにピッタリのエリアは?広島市内のおすすめ地域 子育てを意識して引っ越しを検討する際は、保育園や学校が近くにあることはもちろん、自然の多さも重要な判断基準です。 また地域の安全性も欠かせません。 子育てに合った環境を選ぶことで、毎日の暮らしにゆとりと安心が生まれます。 そこで、ここでは子育て世代におすすめのエリアをご紹介します。 安佐南区・西区など郊外エリアが狙い目 広島市中心部へのアクセスも良好でありながら、緑が多く、閑静な住宅街が広がる安佐南区や西区が狙い目です。 安佐南区はファミリー世帯が多く住んでおり、緑道公園が長く続いていて和やかな雰囲気がある地域です。 ペットを飼っている方も多く、公園では交流を楽しんでいる方もいます。 また、街の中心部にイオンモール広島祇園があり、ショッピングやグルメを楽しめます。 モール内の飲食店も定期的に入れ替わるため、飽きることがありません。 近隣住民の方からは「無印良品やGUなどの店舗が入っている」「さまざまなグルメが楽しめる」と声が上がっています。 西区は、JRやバス、路面電車など揃っていて広島市の中心地に行きやすいです。 徒歩でも中心地に行くことができます。坂道が少なく平地であることが好評です。 駅近辺の商店街には、スーパーや飲食店、病院などがあり日常生活を送る上で困ることはありません。 昔ながらの下町のため、落ち着いており安心して子育てしたい方におすすめです。 土地選びで気をつけたいポイント 広島市で注文住宅を建てるご予定で、それに向けて土地探しをしている方は子育てしやすいかどうかをチェックするようにしましょう。 土地選びで気をつけたいポイントは4つあります。 (1)保育園・幼稚園の待機状況 待機児童が多いと保育園に入園できないため、引っ越し前に各区役所や保育所へ問い合わせ、入園状況を確認しましょう。 また公立保育園だけでなく、認定こども園や企業主導型保育所など民間施設の有無も確認しておくことをおすすめします。 (2)通学路・通勤路の利便性 お子さんが小学生、中学生になると、徒歩や自転車での通学が増えます。 そのため、学校までの道を歩いてみて歩道の整備状況、信号の有無などを確認してください。 共働きの場合はご夫婦の通勤時間帯にバスや電車の混雑状況を調べ、ストレスなく通勤できるかどうかも考慮しておくと子育てしやすくなります。 (3)災害リスクと防災拠点 広島市は、地域によって洪水や土砂災害のリスクが異なります。 ハザードマップを確認し、自然災害の心配がない場所かを確かめておきましょう。 また、避難所や防災拠点が近くにあるかを把握しておくとより安心できます。 (4)医療機関・子育て支援施設の近さ お子さんが体調を崩した際にすぐ駆け込める小児科や総合病院が近くにあるかどうかを確認しましょう。 さらに、子育て支援センターや児童館などの公共施設が充実しているエリアは、ママ友・パパ友づくりにも役立ちます。 5.まとめ 広島市では、若者世帯が安心して妊娠、出産、子育てができるように、さまざまな支援を提供しています。 出産や育児にかかる費用の一部負担をはじめ、便利なおむつのサブスクリプションサービス、育児管理アプリが提供されています。 また、広島市の中心街を少し離れると、自然が多く閑静な住宅街が広がるため、子育てしやすい環境も整っています。 これから家族を築く方や、子育て世代の方にとって広島市は理想的な街です。 タナカホームズでは、地域特性を最大限に活かした提案を得意としています。 自分たちのライフスタイルに合った住まいはどこなのだろうかとご興味がある方は、ぜひタナカホームズ広島中央店へご相談ください。 【タナカホームズ】広島市の建売住宅をチェック! ★伴東建売住宅(二階建て/3LDK) インダストリアルスタイルのデザインと、柔軟かつ機能的な間取りの3LDK。 2階部分のバルコニーや、玄関からリビングまでつながる土間など、自由な発想が活かされた住空間。 こちらは随時見学受付中。お気軽にお問い合わせください♪ <<ここでしか見られない限定情報公開中 無料会員登録はコチラ>> 会社名:田中建設株式会社 部署名:経営企画部 執筆者名:大勢待 昌也 執筆者の略歴 保有資格 住宅ローンアドバイザー 執筆者のSNSのリンク:https://www.facebook.com/oosemachi
-

2025年6月13日 / 家づくり
広島市で二世帯住宅を検討中のあなたへ | 理想を叶えるための3つのポイント
広島市で近年注目を集める二世帯住宅。 子育て世代と親世代が共に暮らすことで、安心感や経済的メリットを享受できます。 しかし、二世帯住宅は家族間のコミュニケーション、プライバシー、費用など、検討すべき点が多岐にわたります。 この記事では、広島市で二世帯住宅を検討する方へ、メリット・デメリットから間取りタイプ、コストを抑えるコツまで、3つのポイントで解説します。 後悔しない二世帯住宅を建てるために、ぜひ参考にしてください。 目次 1.広島市で二世帯住宅を建てるメリット・デメリット 2.家族にあった間取りタイプはどれ? 3.広島市でコストを抑えつつ理想の二世帯住宅を建てるコツ 4.まとめ 1.広島市で二世帯住宅を建てるメリット・デメリット 二世帯住宅を建てることは、家族にとって大きな決断です。 そのメリットとデメリットをしっかりと理解しておくことが、円満な同居生活を送るための第一歩となります。 同居で得られる安心感と経済的メリット 二世帯住宅には、単に同居する以上のメリットが多岐にわたります。 最大のメリットは、育児や介護における相互扶助です。 子育て世代は親世帯からのサポートで安心感を得られ、親世帯も将来的な介護で子世帯からの助けを期待できます。 互いに支え合うことで、家族全体の安心感が向上します。 次に、経済的なメリットも重要です。 単独で2軒建てるよりも土地代や建築費用を抑えられ、ローンの一本化で金利負担も軽減できます。 光熱費などのランニングコストも効率化でき、共有名義による税制優遇も期待できます。 これらは長期的な家計に大きなプラスです。 さらに、防犯面の安心感も高まります。 常に誰かが家にいることで空き巣のリスクが減り、旅行などで家を空ける際も管理を任せられるため安心です。 また、家族間のコミュニケーションが活発になる点もメリットです。 日常的に顔を合わせることで自然と会話が生まれ、家族の絆が深まります。 祖父母と孫の交流は子どもの成長に良い影響を与え、共に食事やイベントを楽しむことで家族全体の幸福度が高まります。 二世帯住宅でありがちなトラブル 二世帯住宅には、単に同居する以上の多くのメリットがあります。 最大の利点は育児や介護の相互扶助です。 親世帯と子世帯が互いに助け合うことで、急な事態にも安心感が増し、家族全体の安心感が向上します。 次に、経済的メリットも大きく、単独で2軒建てるよりも土地代や建築費用を抑えられ、ローンや光熱費も効率化できます。 税制優遇も期待でき、長期的な家計に貢献します。 さらに、常に誰かがいることで防犯面での安心感も高まり、留守中の心配も軽減されます。 また、日常的に顔を合わせることで家族間のコミュニケーションが活発になり、絆が深まります。 祖父母と孫の交流は子どもの成長に良い影響を与え、共に過ごす時間が家族の幸福度を高めます。 一方で、二世帯住宅には特有のデメリットやトラブルの可能性も存在します。 最も懸念されるのはプライバシーの侵害です。 生活時間や価値観の違いから、音や生活臭が気になったり、お互いの行動が干渉し合ったりすることがあります。 特に、プライベート空間が確保されていないとストレスが溜まりやすくなります。 また、生活費や家事・育児の役割分担に関する問題も起こりがちです。 共有部分の費用分担や、家事・育児の関わり方について事前に明確なルールがないと、不満が生じやすくなります。 人間関係においては、過度な干渉や意見の衝突も起こり得ます。 これらのトラブルを避けるためには、事前に徹底的に話し合い、明確なルールを定めることが不可欠です。 間取りを検討する段階から、各世帯の意見を尊重し、プライバシーの確保と交流のバランスを考慮した設計を心がけましょう。 生活費や家事・育児の分担も具体的に取り決め、定期的に家族会議を開くなど、密なコミュニケーションを継続することが円満な同居生活には不可欠です。 ■こちらもチェック!:ローコストの二世帯住宅を建てる際のコツ|準備すべきこと・コストカットする方法も解説 2.家族にあった間取りタイプはどれ? 二世帯住宅の間取りは、家族間の関係性やライフスタイルによって大きく3つのタイプに分けられます。 それぞれの特徴を理解し、ご自身の家族にとって最適な形を選ぶことが、円満な同居生活を送る上で非常に重要です。 プライバシーを確保できる完全分離型 完全分離型は、二世帯がそれぞれ独立した生活空間を持つ間取りタイプで、最もプライバシーを確保しやすいのが特徴です。 玄関、キッチン、浴室、トイレといった水回りを含むすべての生活空間が分かれているため、まるでアパートが2つ繋がっているようなイメージです。 メリットは、生活時間帯やライフスタイルの違いを気にせず、各世帯がそれぞれのペースで暮らせる点です。 音やニオイを気にせず、来客時も気兼ねなく過ごせます。 また、将来的にどちらかの世帯がいなくなった場合でも、賃貸に出したり売却したりしやすいなど、資産価値の面でも有利です。 一方で、デメリットは、水回り設備が二世帯分必要になるため、建築費用が高額になりやすいことです。 独立した空間を持つ分、延床面積が大きくなりがちで、広い土地が必要になる場合もあります。 広島市内で広い土地の確保が難しい場合や、予算に限りがある場合は慎重な検討が必要です。 また、完全に分離されているため、意識的に交流の機会を作らないと、家族間のコミュニケーションが希薄になる可能性もあります。 コストを抑えて快適に暮らせる一部共有型 一部共有型は、玄関やリビング、浴室、キッチンの一部など、限られた空間を共有するタイプの二世帯住宅です。 たとえば、1階を親世帯、2階を子世帯とし、玄関とお風呂を共有するような間取りがこれに当たります。 メリットは、完全分離型と比べて建築コストを抑えられる点です。 水回りの設備をまとめることで、設備費や工事費を節約できます。 また、共用部分があるため、家族が自然と顔を合わせる機会が増え、適度なコミュニケーションが生まれるため、完全分離型のような交流不足の心配が少ないでしょう。 子育てや介護など、ゆるやかなつながりを保ちながら助け合えるのが魅力です。 一方で、デメリットは、共有部分があることでプライバシーが完全に確保されにくい点です。 共有スペースの使用時間や来客時のマナーなど、事前にルールを決めておかないとトラブルに発展する可能性があります。 お互いの生活音や生活習慣への配慮が求められ、家族間の関係性や価値観の理解、尊重が成功のカギとなります。 家族のつながりを大切にできる完全同居型 完全同居型は、二世帯が玄関やリビング、キッチン、浴室など、すべての生活空間を共有する間取りです。 寝室以外は共有スペースとなるため、一般的な戸建て住宅とほぼ同じ感覚で暮らせます。 最大のメリットは、建築費用を最も抑えられる点です。 設備が一つで済み、イニシャルコストや延床面積を抑えられます。 また、常に家族が顔を合わせるため、コミュニケーションが活発になり、家族の絆が深まりやすいのも魅力です。 子育て支援や介護の協力も自然に行え、温かい家族関係を重視するご家庭に最適です。 しかし、プライバシーの確保が最も難しい点が大きなデメリットです。 生活リズムや価値観の違いからストレスが生じやすく、水回りの利用や来客時の気遣いなどでトラブルになる可能性もあります。 特に子育て世代は、親世帯からの干渉が負担になることも。 完全同居型を選ぶ際は、家族間の良好な関係性が不可欠です。 お互いの性格や生活習慣を深く理解し尊重し合えるか、事前にプライベート空間や生活費の分担について徹底的に話し合い、希望をすり合わせることが重要です。 3.広島市でコストを抑えつつ理想の二世帯住宅を建てるコツ 二世帯住宅は一般的な住宅に比べて費用が高くなる傾向がありますが、広島市で賢くコストを抑えながら理想の住まいを実現する方法はいくつか存在します。 地元の工務店や住宅メーカーに依頼してみる 現在お住まいの家を建てた工務店や住宅メーカーが二世帯住宅の実績を持つなら、まずそこに相談するのがおすすめです。 その理由は次の3点です。 ● 既存情報を把握することで調査や設計の手間、予期せぬ追加工事のリスクが減り、費用削減に繋がる可能性がある ● 過去の取引で既に信頼関係があるため、スムーズなコミュニケーションが期待でき、新たな業者を探す手間が省ける ● 長年の顧客として特別な割引を受けられたり、過去の実績から資材調達や職人手配が効率化され、結果的にコストダウンに繋がったりするケースもある ただし、元の業者の二世帯住宅実績が少ない場合や、希望のデザイン・性能に合わない場合は、複数の業者から見積もりを取り、比較検討しましょう。 その際は、二世帯住宅の実績が豊富な業者を選ぶのが賢明です。 広島市で活用できる『三世代同居・近居支援制度』を活用してみる 広島市は、三世代同居・近居を促進する独自の支援制度を設けており、これを活用することで二世帯住宅の建築費用や住宅ローンの負担軽減が可能です。 主な制度として「広島市三世代同居・近居支援事業補助金」があります。 ● 対象: 小学生以下のこども(出産予定のこどもを含む。)がいる世帯が、広島市内に住む親元近くに住み替えて同居又は近居を始める場合 ● 補助金額:助成対象費用の1/2(上限10万円) この補助金は、上限10万円単位の助成が期待でき、建築費用を抑える有効な手段です。 補助金活用のポイントとして以下が挙げられます。 ● 補助金制度は年度で内容や募集期間が変わるため、必ず広島市の公式サイトや窓口で最新情報を確認しましょう ● 対象となる世帯・建物の条件、手続きの流れを詳細に確認することが重要 ● 住宅メーカーや工務店、ファイナンシャルプランナーなどに相談し、適切なアドバイスを受けることがおすすめ これらの制度を積極的に活用することで、広島市での二世帯住宅の経済的負担を軽減し、より豊かな生活を実現できます。 4.まとめ 広島市で二世帯住宅を検討するなら、家族の絆を深め、支え合う大きなメリットがあります。 育児・介護の相互扶助、経済的負担の軽減、防犯性の向上など、魅力は多い一方で、プライバシー確保や生活費分担といった課題も考慮が必要です。 円満な二世帯生活には、家族構成とライフスタイルに合わせた間取り選びが重要です。 完全分離型で独立性を保つか、一部共有型で適度な交流を促すか、完全同居型で常に家族の温かさを感じるか、最適な選択肢を見つけましょう。 また、広島市で理想の二世帯住宅をコストを抑えて建てるには、既存の工務店への相談や、広島市の「三世代同居・近居支援制度」といった補助金活用も有効です。 二世帯住宅は、家族の未来をデザインする大切な計画です。メリット・デメリットを理解し、家族間で話し合い、専門家のアドバイスも参考にしながら、後悔のない理想の住まいを実現してください。 タナカホームズ広島中央店では、お客様のライフスタイルに寄り添った住まいをご提案いたします。 広島市やその近辺で新築住宅をご検討の方は、お気軽にご相談ください。 【タナカホームズ】広島市内の分譲地をチェック! ★ティーズコート 中山分譲地(広島市東区) 中山小学校まで約1km。子育て世帯に嬉しい立地です♪ ★ティーズコート 伴東分譲地(広島市安佐南区) 伴東小学校まで約900m。お買い物施設も充実な住宅街です♪ <<ここでしか見られない限定情報公開中 無料会員登録はコチラ>> 会社名:田中建設株式会社 部署名:経営企画部 執筆者名:大勢待 昌也 執筆者の略歴 保有資格 住宅ローンアドバイザー 執筆者のSNSのリンク:https://www.facebook.com/oosemachi
-

2025年6月11日 / 家づくり
広島で狭小住宅という選択肢。予算や間取りでわかる納得の選び方
広島市でマイホームを検討する際、「土地がなかなか見つからない」「予算内で希望の広さの家が建てられない」といった悩みに直面する方も少なくありません。 そんな時に検討したいのが、狭小住宅という選択肢です。 限られた土地を最大限に活用し、住む人のライフスタイルに合わせた快適な空間を実現する狭小住宅は、特に都市部である広島市において、現実的な解決策として注目を集めています。 この記事では、広島市で狭小住宅を選ぶメリットやデメリット、費用の目安、そして納得の家づくりを進めるためのポイントを詳しく解説していきます。 目次 1.広島市で狭小住宅が選ばれる理由 2.広島市で狭小住宅を建てる際の費用の目安 3.狭小住宅のメリット・デメリット 4.まとめ 1.広島市で狭小住宅が選ばれる理由 広島市で狭小住宅が選ばれる理由とは何でしょうか。 ここでは、狭小住宅とはなにか、土地価格の高騰と狭小住宅との相性についてご紹介します。 そもそも『狭小住宅』とは? 「狭小住宅」とは、一般的に15坪(約50平方メートル)以下の狭い土地に建てられる住宅のことを指します。 坪数に明確な定義があるわけではありませんが、敷地の形状が特殊な場合や、都市部の細い路地に面した土地に建てられるケースも多く見られます。 限られたスペースを有効活用するため、縦の空間を意識した3階建てやスキップフロア、屋上庭園など、工夫を凝らした設計が特徴です。 採光や通風、プライバシーの確保など、狭いからこそ考え抜かれた設計アイデアが詰まっており、「狭い」という言葉のイメージとは裏腹に、非常に豊かで快適な暮らしを実現できる可能性を秘めています。 土地価格の高騰と狭小住宅の相性 広島市は、中国地方最大の都市であり、その利便性の高さから人口が集中し、それに伴い土地価格も高騰しています。 特に、交通アクセスが良好な都心部や人気エリアでは、広々とした土地を手に入れるのは非常に困難であり、予算オーバーになってしまうことも少なくありません。 このような状況において、狭小住宅は非常に現実的な選択肢となります。 広い土地に比べて坪単価が抑えられる傾向にある狭い土地を活用することで、総費用を抑えつつ、希望するエリアに住まいを持つことが可能になります。 また、変形地や旗竿地など、敬遠されがちな土地でも、設計の工夫次第で魅力的な住空間へと生まれ変わらせることができます。 土地の選択肢が広がることで、より理想に近い立地で家を建てられる可能性が高まるのです。 土地の有効活用という観点からも、狭小住宅はこれからの広島の住宅事情にフィットする、賢い選択肢と言えるでしょう。 2.広島市で狭小住宅を建てる際の費用の目安 広島市で狭小住宅を建てる際にどのくらいの費用がかかるのかが気になるところです。 ここでは、費用の目安とエリア別の価格の違いをご紹介します。 建築費用+土地代で見る費用感 狭小住宅の総費用は、「土地代」と「建築費用」の合計で決まります。 広島市内で狭小住宅を建てる場合、これらの費用はどのくらいになるのでしょうか。 まず、土地代ですが、狭小住宅を建てるような狭い土地は、広い土地に比べて坪単価が割安になる傾向があります。 しかし、広島市内の立地条件によって大きく変動します。 例えば、中心部の商業地域や駅に近いエリアでは、坪単価が非常に高くなるため、狭い土地であっても数千万円単位の費用がかかることも珍しくありません。 一方、郊外や駅から少し離れた住宅地では、坪単価が下がるため、土地取得の費用を抑えることができます。 次に、建築費用についてです。 狭小住宅は、一般住宅に比べて坪単価が高くなる傾向があります。 これは、限られた空間を最大限に活用するための特殊な基礎工事や構造計算、高機能な設備、複雑な設計などが求められるためです。 例えば、3階建てにする場合の構造強化、階段や水回りの配置の工夫、収納スペースの確保、採光・通風を考慮した窓の配置など、一般的な住宅ではあまり考えないような設計上の工夫が必要になります。 具体的な費用の目安としては、広島市内で狭小住宅を建てる場合、土地代と建築費用を合わせて3,000万円から5,000万円程度を一つの目安として考えることができます。 もちろん、これはあくまで目安であり、土地の広さや立地、建物の仕様、ハウスメーカーや工務店によって大きく変動します。 例えば、デザイン性の高い家や、高性能な設備を導入する場合は、さらに費用がかさむこともあります。 そのため、具体的な予算を立てる際には、複数のハウスメーカーや工務店から見積もりを取り、それぞれの費用の内訳を詳細に比較検討することが重要です。 ■こちらもチェック:広島市の注文住宅|価格相場&坪単価を徹底解説! エリア別価格のちがい 広島市は広範囲にわたり、中心部から郊外まで様々な特性を持つエリアがあります。 当然、それに伴い土地価格も大きく異なります。 狭小住宅の費用を考える上で、このエリアによる価格差を理解しておくことは非常に重要です。 例えば、広島市中区の紙屋町や八丁堀といった都心部に狭小住宅を建てる場合、利便性はよいですが、土地代が非常に高額になるため、総額で5,000万円を超えるケースも少なくありません。 一方で、安佐南区の祇園や佐伯区の五日市など、都心から少し離れたエリアであれば、土地代を抑えつつ、十分な広さの狭小住宅を建てられる可能性が高まります。 このように、エリアによって土地価格の相場が大きく異なるため、まずは「どのエリアに住みたいか」を明確にし、そのエリアの土地相場をしっかりとリサーチすることが、無理のない資金計画を立てる第一歩となります。 不動産情報サイトや地元の不動産会社に相談し、具体的な坪単価や物件情報を集めることをおすすめします。 3.狭小住宅のメリット・デメリット 狭小住宅は、その特性上、一般的な住宅にはないメリットとデメリットを併せ持っています。 これらを十分に理解した上で、自分たちのライフスタイルに合っているかを見極めることが、後悔しない家づくりの鍵となります。 暮らしやすさや光熱費削減などのメリット 狭小住宅には、限られたスペースだからこそ得られる多様なメリットがあります。 ● 土地代を抑え、都心部に住める可能性が高まる ● 固定資産税の負担が軽減される ● 光熱費の削減 ● 掃除やメンテナンスが楽 ● プライバシーの確保と防犯性の高さ ● 設計の自由度が高い 狭小住宅は「狭い」というイメージがありますが、設計の工夫によって快適な家づくりをすることができます。 収納や空間の狭さなど注意点と対策 一方で、狭小住宅特有のデメリットも存在します。 これらを事前に把握し、対策を講じることが重要です。 以下に狭小住宅特有のデメリットをまとめてみました。 上記のように、対策を取ることで狭小住宅でも快適に過ごすことができます。 ■こちらもチェック:ビルトインガレージのある木造3階建ては安全?耐震性や特長、設計時の注意点を解説 4.まとめ 広島市でマイホームを検討する際、土地価格の高騰や限られた予算の中で理想の住まいを手に入れることは、決して簡単なことではありません。 しかし、今回ご紹介した「狭小住宅」という選択肢は、これらの課題に対する有効な解決策となり得ます。 狭小住宅は、限られた土地を最大限に活用し、住む人のライフスタイルに合わせて空間を創造することができます。 土地代を抑えつつ、都市部の利便性を享受できる可能性があり、ランニングコストの面でも優位性があります。 もちろん、空間の狭さや日当たり・風通しといったデメリットも存在しますが、これらは設計の工夫や専門家の知恵を借りることで、十分に解決できる問題です。 重要なのは、ご自身のライフスタイルや家族構成、将来の計画をしっかりと見据え、メリットとデメリットを比較検討することです。 広島市内で狭小住宅を検討する際は、実績豊富なハウスメーカーや工務店、設計事務所に相談し、ご自身の希望を具体的に伝えることから始めてみましょう。 きっと、限られたスペースだからこそ実現できる、あなただけの理想の住まいが見つかるはずです。 広島で新しい暮らしをスタートさせるために、狭小住宅という選択肢をぜひ前向きに考えてみませんか? タナカホームズ広島中央店では、土地形状はもちろん、ライフスタイルに合わせた快適な住まいをご提案いたします。 広島市内で新築住宅をご検討の方は、お気軽にご相談くださいませ。 【タナカホームズ】広島市内の分譲地をチェック! ★ティーズコート 中山分譲地(広島市東区) 中山小学校まで約1km。子育て世帯に嬉しい立地です♪ ★ティーズコート 伴東分譲地(広島市安佐南区) 伴東小学校まで約900m。お買い物施設も充実な住宅街です♪ <<ここでしか見られない限定情報公開中 無料会員登録はコチラ>> 会社名:田中建設株式会社 部署名:経営企画部 執筆者名:大勢待 昌也 執筆者の略歴 保有資格 住宅ローンアドバイザー 執筆者のSNSのリンク:https://www.facebook.com/oosemachi
-

2025年6月4日 / 土地
広島市で平屋って現実的?迷ったら知っておきたいポイントを解説!
近年、平屋の人気が高まっています。 平屋は階段の上り下りがなく、小さな子どもや高齢者に優しいバリアフリーな住まいであり、地震にも強い特徴があるため注目されています。 今回は、平屋が注目される理由や価格と広さの目安、平屋に適したエリアを紹介します。 ぜひ、広島市内で平屋を検討している方は参考にしてください。 目次 1.いま平屋が注目される理由とは? 2.広島市で平屋を建てるならこれくらいかかる!価格と広さの目安 3.平屋にピッタリのエリアは?広島市内のおすすめ地域 4.まとめ 1.いま平屋が注目される理由とは? 以前は、高齢者向けの住まいというイメージが強かった平屋ですが、今は若い世代からも支持されている人気の住まいに変わってきています。 最初に、平屋が人気の理由を解説します。 ワンフロアで完結する快適さと暮らしやすさ 平屋の最大の特徴はすべての生活空間がワンフロアで完結することです。 階段の上り下りの移動がないため家事が効率的になり、掃除が楽になります。 特に、洗濯は重い洗濯物を持って階段を上り下りする必要がないため家事動線が効率的です。 また、階段がない分、小さな子どもや高齢者に優しいバリアフリーな住まいと言えます。 将来、高齢者になった場合を想定して、階段での移動が必要な2階建て・3階建ての住宅より「一生暮らす家」として平屋を検討する方も増えています。 さらにリビングや寝室、子ども部屋が同じフロアにあるので、家族と顔を合わせる機会が増え、自然とコミュニケーションが取りやすいのもメリットです。 地震に強い構造で安心感も◎ 日本は地震大国であり、広島でも過去に大きな地震が発生しています。 そのような背景から住宅選びにおいて耐震性は欠かせない仕様の条件です。 平屋は、構造的に地震に強く、安心して暮らせる住まいとして評価されています。 二階建てと比べて、建物の高さが低く重心が地面に近いため、地震の揺れによるダメージを受けにくい特徴があります。 また、平屋は正方形などのシンプルな構造を採用している場合が多く、振動が分散されるので変形するリスクが軽減します。 一方、複雑な形をした建物は、振動を上手に分散できず特定の箇所に力が加わり、変形することも少なくありません。 そのため、倒壊リスクが高くなる危険性が生じてしまいます。 ■こちらもチェック!:【実例付き】注文住宅で平屋を建てる際の相場を紹介!価格が左右するポイントやコストを抑えるコツもあわせて解説 2.広島市で平屋を建てるならこれくらいかかる!価格と広さの目安 平屋を建てる際に、多くの方が気になるのがどのくらいの広さが必要か、費用はいくらかかるのかといった点ではないでしょうか。 家族構成やライフスタイルによって必要な延べ床面積は異なり、建築費用も変わってきます。 次に、広島市の平屋の広さと価格の目安、コストを左右する要因について解説します。 広島市の平屋の平均的な延べ床面積 平屋を建てる際に最初に気になるのが、建物の広さ(延べ床面積)の目安です。 「e-Stat 政府統計の総合窓口」の令和5年度住宅・土地統計調査によると、広島市の1住宅あたりの延床面積は80.01㎡(24.2坪)になります。 また、国土交通省の住生活基本計画では、快適な暮らしを送るために必要な戸建住宅の広さを掲載しています。 その計算式(一般型誘導居住面積水準 2人以上の世帯:25㎡×世帯人数+25㎡の計算式)をもとに世帯人数の坪数は以下になります。 参考データ:国土交通省の「住生活基本計画における居住面積水準」 平屋を検討されている方は、世帯人数に合わせて上記の坪数も併せて参考にしてみましょう。 広島市の平屋の平均的な建築費用 次に気になるのが、広島市の平屋の建築費用の目安です。 住宅金融支援機構の「2023年度のフラット35利用者調査」によると、広島県で注文住宅を建てた方の平均建設費(建物にかかる費用)は、約3,959万円です。 平均住宅面積は121.3㎡(約36.6坪)のため、平均坪単価は108.1万円になります。 平屋の平均坪数は20~30坪程度が多いため、約2,200~3,200万円を建築費の目安と考えておくと良いかもしれません。 住宅の仕様によって金額は変動しますので、ひとつの目安として参考にしてください。 仕様や立地、地形などコストを左右する要因 広島市で平屋を建てようと検討した際には、建物本体の価格だけではなく、どのような仕様や立地・地形を選ぶかによって最終的な費用が異なります。 それぞれどのように価格と関係しているか見ていきましょう。 1. 仕様と住宅性能の関係 平屋は階段が不必要なため構造がシンプルですが、内装や設備のグレードを上げれば、建築費は高くなります。 例えば、隣家との距離が近い場合は、1階建てである平屋は十分な採光を確保できません。 吹き抜けや天窓を設置する必要があり、こうした設備を増やすことで建築費は高額になるでしょう。 また、吹き抜けやロフトの設置は住宅性能のグレードにも影響します。 これらの仕様は、天井を高くして縦の空間を活用することが一般的です。 開放的な空間を作るには有効ですが、空調の効き目を低下させます。 そのため、設備のグレードを上げて気密性や断熱性を高めなければいけません。 建材のグレードを上げてしまうと、当然、建築費が高くなってしまいます。 2. 立地条件 平屋を建築する際には、土地選びと法規制の確認が大切です。 平屋は広い敷地面積が必要なため、都市部よりも郊外の方が適しています。 しかし、郊外でも日当たりや風通しの良さ、周辺環境を考慮する必要があります。 また、建築基準法や自治体の条例による高さ制限や建蔽率、容積率を確認しておくと良いでしょう。 3.地形や地盤の状態 平屋は2階建てよりも建物の基礎面積と屋根面積が広くなるため、基礎工事や屋根工事の費用が高くなりやすい傾向があります。 また、土地の傾斜や変形地の場合は、造成費用や特殊な基礎構造が必要になる場合があります。 ■こちらもチェック!:【実例つき】おしゃれな平屋の魅力とポイント!山口・広島・島根で実現する方法 3.平屋にピッタリのエリアは?広島市内のおすすめ地域 平屋は建物の広さだけではなく、周辺環境やエリアの特徴も土地選びには重要です。 広島市内で平屋に適したエリアを探す際には、自然環境と利便性のバランスが取れた郊外地域に注目しましょう。 ここでは、広島市で平屋に適しているエリアと土地選びで気をつけたいポイントを紹介します。 安佐南区・西区など郊外エリアが狙い目 広島市内で平屋を建てる際には、安佐南区や西区などの郊外エリアは比較的広い土地を確保しやすく、平屋に適した地域とされています。 これらのエリアでは、自然環境が豊かで静かな住環境を求める方に人気があります。 紹介した2つのエリア以外でも広島市内では住環境に適したエリアがあるので、範囲を広げて探してみるのも良いかもしれません。 土地選びで気をつけたいポイント 敷地面積以外にも平屋に適した土地の特徴を紹介します。 平屋に向いている土地を見極めて、メリットを活かした住宅を建てるようにしましょう。 ■こちらもチェック!:広島市の注文住宅|価格相場&坪単価を徹底解説! 4.まとめ 平屋住宅は、ワンフロアで暮らしやすい、地震に強い構造などさまざまな魅力を備えた住まいです。 しかし、広島市で平屋を建てる際には、世帯人数に応じた適切な広さと予算感を把握し、仕様や土地の条件によってコストが変動することを理解しておきましょう。 また、日当たりや地盤の強度など土地選びのポイントを押さえることで、快適で長く暮らせる住まいづくりが可能になります。 広島市内には安佐南区や西区などのエリアは、広い土地を確保しやすく、自然と利便性のバランスが取れた平屋向きの地域として注目されています。 理想の平屋住宅を実現するには、地域の特性をよく知る住宅会社と相談しながら、じっくりと計画を進めることが成功への近道です。 タナカホームズでは、ライフスタイルに寄り添った住まいをご提案いたします。 広島市内で新築住宅をご検討の方は、タナカホームズ広島中央店までお問合せください。 【タナカホームズ】広島市内の分譲地をチェック! ★ティーズコート 中山分譲地(広島市東区) 中山小学校まで約1km。子育て世帯に嬉しい立地です♪ ★ティーズコート 伴東分譲地(広島市安佐南区) 伴東小学校まで約900m。お買い物施設も充実な住宅街です♪ <<ここでしか見られない限定情報公開中 無料会員登録はコチラ>> 会社名:田中建設株式会社 部署名:経営企画部 執筆者名:大勢待 昌也 執筆者の略歴 保有資格 住宅ローンアドバイザー 執筆者のSNSのリンク:https://www.facebook.com/oosemachi
最近の投稿